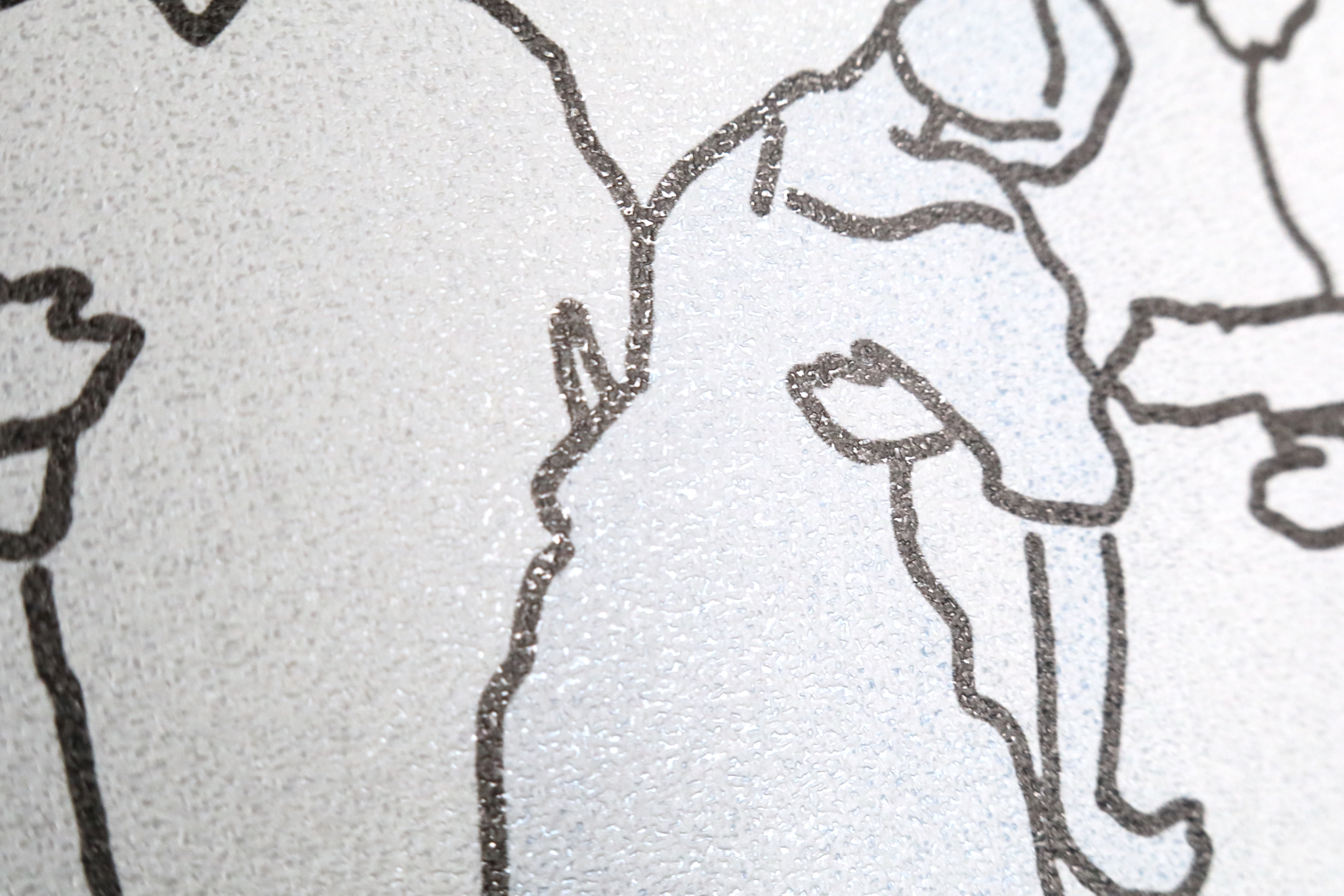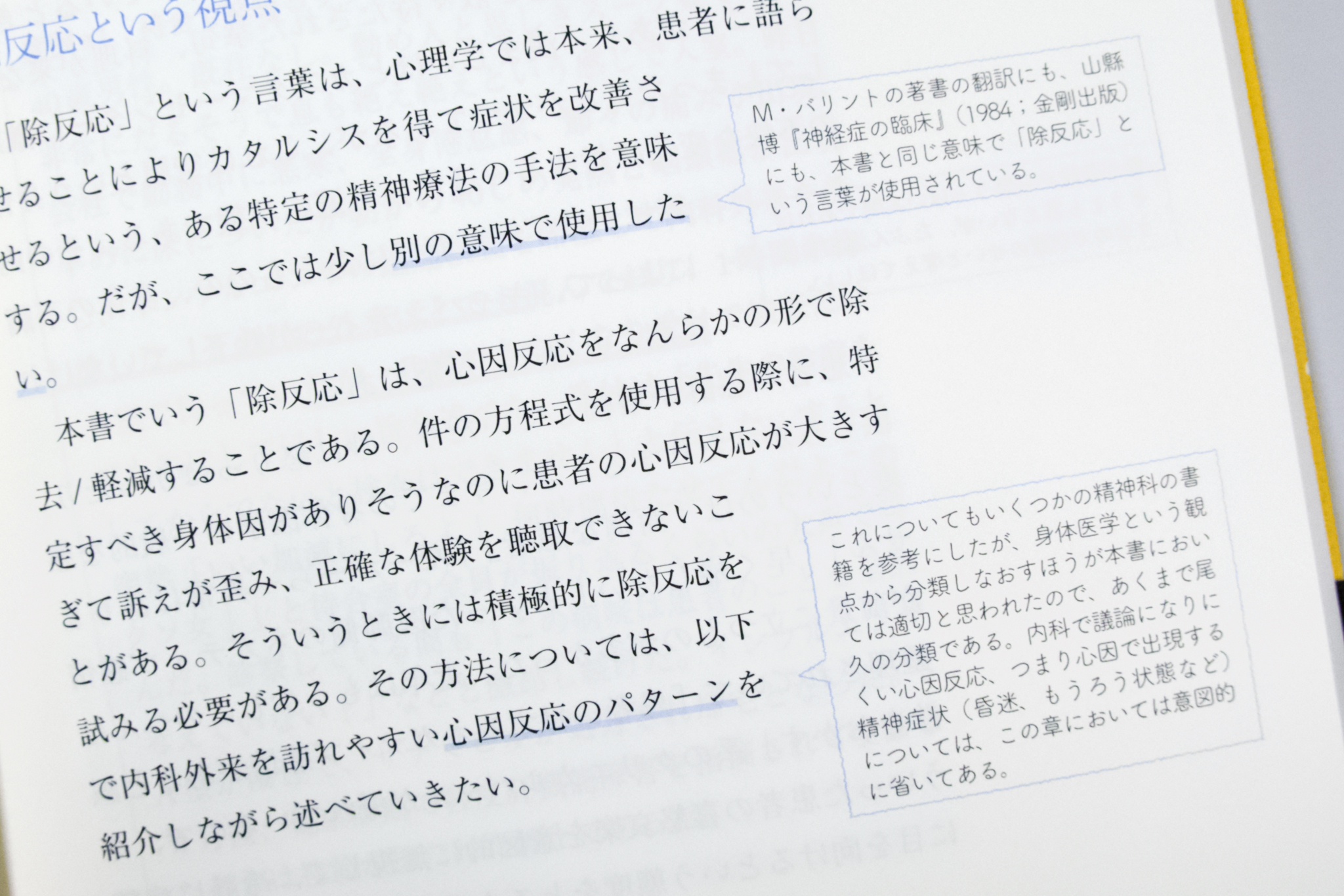器質か心因か

表紙買いの一冊。電子版より冊子体がオススメ。
Amazonのオススメにチラチラでてきていて、他の医学書と書影が並ぶと違和感著しい。一見すると素人さんの作った町内会の会報の表紙のようだが、どうも変だ。金芳堂の中のヒトもハマっていた。
書名や帯の文字は手書きにみえる。検索すると、フリーフォントの851マカポップを斜体にして使ったらしい。そうらしいのだけれど、書名の「か」だけ手を加えてある。「か」に重きが置かれている? 少なくとも、イラレで文字をアウトライン化して形を変えるくらいはできないとこうはならない。
カバーの紙にになにかテクスチャがあるらしいのは、SNSにいくつかあがっていた本の写真でみてとれた。実物をみると、ざらざらで、キラキラしていて、少し透明感がある。御影石に似ている。中外医学社の中のヒトによると、タントセレクトTS-6という用紙らしい。
イラストは、マウスでぎこちなく描かれたようにみえる。しかし、これには元ネタがあって、「シャルコーの臨床講義」という19世紀の油彩画だ。中央の転換性障害っぽい女性だけが少し青い。印刷だろうか?…ネタバレになるのでここでやめておこう。
判型も特殊で、上下が少し詰まったA5変形(実測149×188mm)。ページを繰ると、いよいよ変だ。傍注がたくさんある。たくさんあるだけではなく、本文に食い込んでいて、読み飛ばすわけにはいかない。こっちに筆者の本心が書かれているのだろうか。逸れがちな話を一筋にするのが面倒だったのだろうか。本文より注の方が多いという本はあるけれども(例)、注の主張が強いのはめずらしい。判型の幅が広いのは、この注を入れるためだろうか。
『器質か心因か』という書名自体が「釣り」である。これに救いを得られそうに感じる医師は少なくないだろう。身体的な症状の原因が心の問題であったり、精神的な症状の原因が身体の病変であったりして、診断の難しいことがあるのだ。そして、そんな「二元論」で考えてはいけないと、まえがきで裏切ってみせる。文の主語が「私」であることが多く、診療マニュアルというよりはエッセイだ。筆者も「読み物」だといっている。
著者の尾久氏は精神科の医師で、内科の外来でこういう難しい症例をみておられる。精神科医を父に持ち、その書斎や務めている病院の図書室の古い蔵書、内科医の國松淳和氏との症例の省察に学んだという。詩人でもある。めんどくさそうだ。神経関係の医師で詩人でもある場合、めんどうになるのかもしれない(怪談に学ぶ脳神経内科)。
本書の軸になるのは、筆者の提唱する方程式だ:
心因反応の大きさ = 患者のもともとの脆弱性 + 身体因の脳への侵襲 + 心因
ことばでいうと、
脆弱性に身体因と心因が加わり、ある閾値を超えると心因反応が起こる
となる。これを多数の症例を引いて解読していく(一部は、診断までいかない。「中学生日記」のようだ)。そして患者を治療にもちこむための考え方が語られる。印象的な言葉が傍注にあった。日和って「○○病は否定できない」と予防線を張るのはだめだという件で:
もし○○病だったら「僕」の責任になってしまうじゃないか、と思う人がいるかもしれないがそんなの当たり前だろう
やはり、傍注に本心がありそうだ。