ネッター解剖学カラーリングテキスト 原著第3版
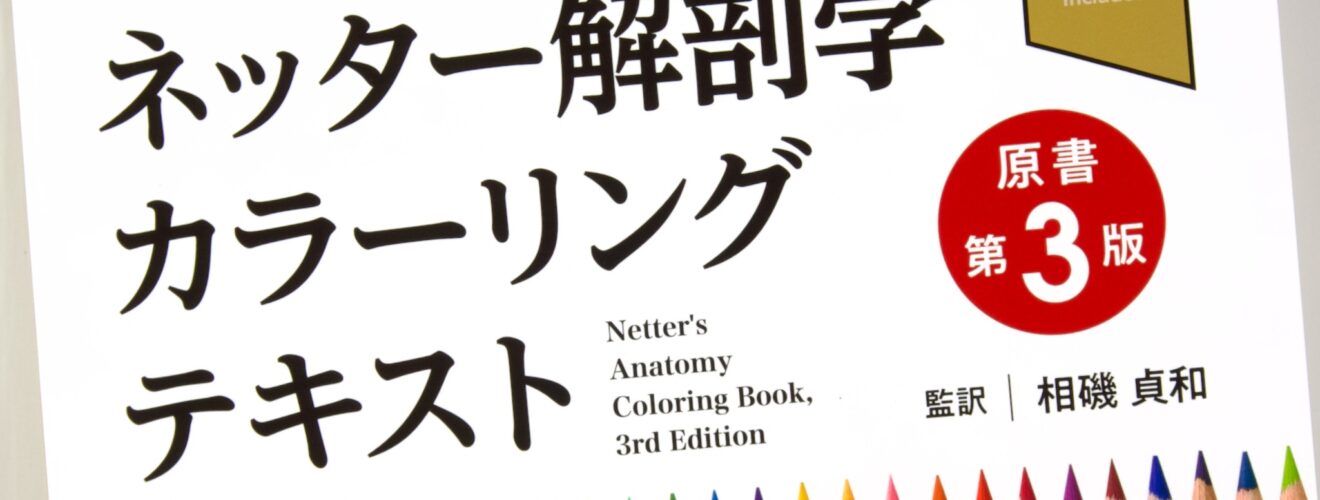
塗り絵をしながら解剖学を学ぶテキスト。同様のテキストはいくつかあるが、本書は『ネッター解剖学アトラス』の図版をトレースした白黒のイラストが使われている。イラストは全部で162点ある。
もとのアトラスは局所解剖学の並びになっているが、本書は系統解剖学だ。つまり、医学科の解剖学実習のコンパニオンとしてよりも、保健学科などの授業があっているだろう。局所解剖学のほうがよければ、『グラント解剖学カラーリングブック』を試してみよう。
本書を解剖学のハードコアなテキスト、たとえば『グレイ解剖学』や『臨床のための解剖学』の代わりに使うというのには、知識がたらなりそうだ(指定教科書になっている場合は別として)。楽しく暗記するコンパニオンとして使おう。本を端から端まで塗ろうと考えるより、試験や試問にでそうな暗記のポイントをやっていったらいいと思う。
たとえば、神経や血管の枝など、細かな塗り絵をしていると、解剖実習で剖出をするのと似た体験と感じられる。下絵を色鉛筆で塗っていくと、本をぼうっと眺めていたのでは気づかないディテールを発見できるはずだ。ふつうの教科書だとイラストをざっとみわたして細部を見過ごしがちだが、そこに手作業が入るとディテールに注意が向くからだろう。
物事を学ぶには、いくつかの方法があって、ひとそれぞれに好みがある。どの方法が合っているのか簡単に診断できるのが、VARKだ。VARKのうちKinetstheticのスコアの高い人なら、特に楽しく本書を使えるだろう。
- Visual 視覚的なものに惹かれる
- Aural 聞いたり話したりするのが好き
- Read/Write 読んだり書いたりするのが好き
- Kinesthetic 動いたり作業したりが好き
冊子のイラストを色鉛筆やマーカーで彩色してしまうと、失敗したり裏映りしたりしたときにちょっとへこむ。最初に塗り始めるのに躊躇する。コピーして使うにはコストがかさむ。幸い本書には、電子版が附属している。英語版しかないが、塗り絵には関係ない。英語の解剖学用語に日本語を書き添えていけば、解剖学用語の書き取り練習にもなる。まあ、日本語版も附属していたらよかったのだが。
そういうわけで、電子版を使って塗り絵を試してみよう。iPadのeBooks+アプリに本書を登録し、イラストを選んで拡大表示し、画面をキャプチャーする。これをノートやイラストのアプリに貼り込んで、色塗りをしていく。アプリによって塗りやすさは違うけれども、使い慣れたのを使えばいいだろう。精密なイラストを描けるアプリより、簡単な描画機能だけのアプリの方が、塗るのに神経を使わずに済む。
Goodnotes 6はノートアプリ。手書きノートに図や写真を貼り込んで自分用の学習ノートをつくったりするのに使える。『Dr. Eggs ドクターエッグス』にもでてくる。半透明の色を塗れるマーカーツールに細い線のがないのが、細かい部分の彩色には難点。iPadだけでなく、iPhone、Macとも同期できる。
フリーボードはAppleの標準アプリで、大きさ無制限の仮想のホワイトボードの上にイラストや写真などを貼り込め、フリーハンドで描き込める。Appleの標準の描画ツールはシンプルだが使いやすい。iPadだけでなく、iPhone、Macとも同期できる。
(権利関係を考慮し表紙の一部の画像のみ使用しています)
