Anatomy – なぜ logy じゃない?
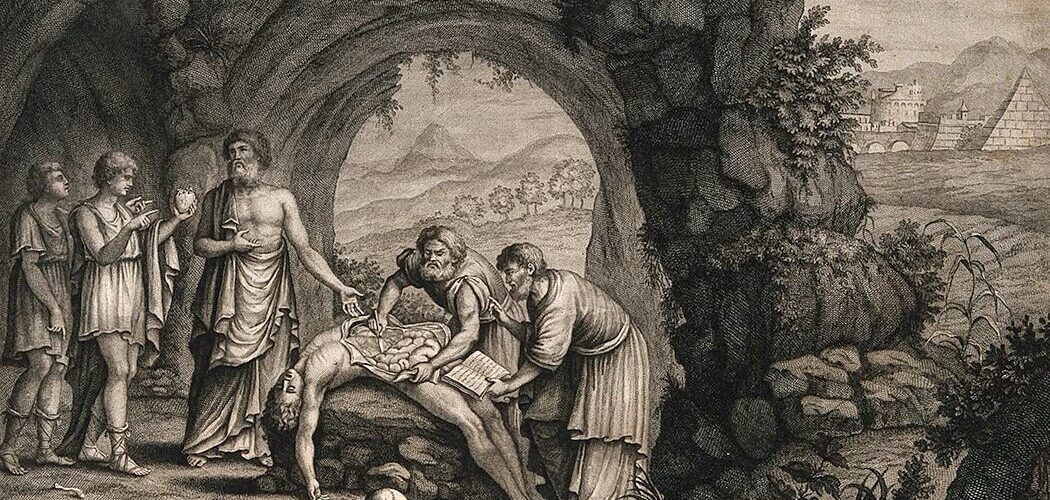
このブログのタイトルでもあるAnatomyだけれど、Anatomyには「logy」「ics」もつかない。日本語では「解剖学」といい、医学の一分野のはずだが、学生には暗記科目と揶揄されるし、もしかして学問とみなされてない?
語源を辿る
英語 anatomy は、Old English の anatomie に由来し、これは古フランス語 anatomie を経て、または ラテン語 anatomia から直接伝わった。これはさらに古代ギリシャ語 ἀνατομία (anatomía) に遡る。これをパートに分解すると
ἀνα- (ana-:上へ、開く) + τομή (tomē:切ること)
となり、直訳すれば「切り開くこと」。
もともと「死体を切開して内部構造を明らかにする行為」という手技を差していて、学問を意味してはいなかった。のちの解剖学の発展により、手技の名称がそのまま学問領域を指すようになったようだ。
日本では、明治4年(1871年)、東京医学校(のち東京大学医学部)がドイツ医学を導入し、ドイツ語 Anatomie の正式訳として「解剖学」が採用された。そのときにはAnaomyは学問になっていたので、日本語には「学」がついたのだろう。英語の dissection に相当する手技をいうときは「解剖」「解剖する」と使い分けられる。
Tome
古代ギリシャ語の Gk.temnein【動】「切る」、Gk.tomos【名】「切断」には、他にも用例がある。
- Atom(原子):L.Gk.atomos(これ以上切り分けられない);a (not) + temnien (切る)
- Epitome(典型):Gk.epitome(要約);Epi(in addition)
-icsと-logy
接尾辞の -ics は、「学問名」や「技術分野名」を表す。ギリシャ語の形容詞語尾 -ikos(~に関する、~の性質をもつ)に遡り、ラテン語の -icus を経由して英語に入った。元は形容詞化する語尾だったが、後に学問や技術体系を指す名詞として固定化した。「体系・技術・実践分野」まで広く含み、学問以外にも活動や技芸に用いられる(athletics, politics など)。
接尾辞の -logy は、ギリシャ語 λόγος (lógos: 言葉・論理・学問)に由来。「~についての論」「~の学問」という明確な「研究・論理」の意味に使われる。
-icsはギリシャ・ローマ時代の四科(quadrivium)に由来する古典的技芸的学問で多く用いられた(mathematics, mechanics, politics, rhetorics など)。-logyは学問的・体系的な領域で多用された(theology、chronology など)。ルネサンス以降〜近現代では、基礎理論は -logy(biology、sociology、immunology など)、工学・技術は -ics (electronics、robotics、proteomics など)が使われることが多い。
Anatomy 小史
Anatomyが学問の体裁を得るまでの経緯をふり返ってみる。
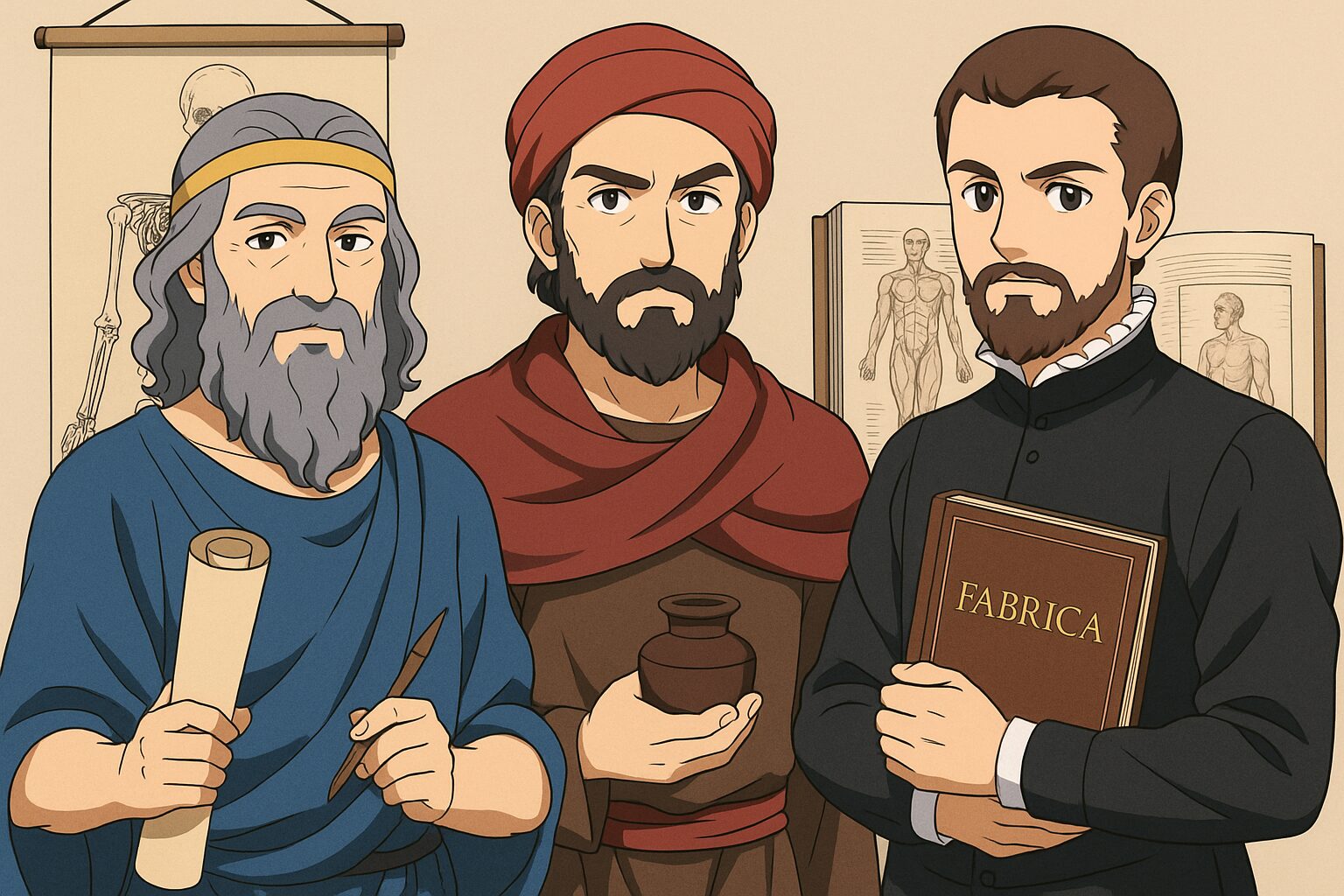
ヘロフィロス, ガレノス、ヴェサリウス:ChatGPTによる想像図
紀元前4~3世紀|アレクサンドリア(エジプト)
ヘロフィロス(Herophilus)は、エラシストラトス(Erasistratus)とともにアレクサンドリア医学校を創設し、プトレマイオス朝の庇護のもと人体解剖が許され、史上初めて系統的な人体解剖を行った。その著作は現存していないが、ガレノスの著作に多く引用されている。ヘロフィロスは duodenum(十二指腸)、retina (網膜)など、現在も使われている解剖学用語を多数創案した。
2~3世紀|ローマ帝国
ガレノス(Galen)は、過去の医学をまとめ、多くの解剖に基づいて体系的な医学を確立した。しかし人体解剖は禁制だったために、骨格系以外は動物の解剖に基づいた部分が多く、誤りも少なくなかった。ガレノスの著作はギリシャ語で記載されていたため、東ヨーロッパには継承されたが、ラテン語を使う西ヨーロッパでは失われた。その後アラビア語を経てラテン語に翻訳され、西ヨーロッパに再導入された。そこでガレノスの医学が聖典化し、科学としての解剖学は1,000年以上停滞した。人体解剖がなされることはあっても、ガレノスの原典に反する所見は変異や手技上の誤りとされた。
16世紀|パドバ(イタリア)
アンドレアス・ヴェサリウス(Andreas Vesalius)は自らヒトの解剖を行い、ガレノスの解剖学が多く動物に基づいていることを指摘した。そして解剖学を実地に基づいて再構築した。その著書『De humani corporis fabrica』は、精緻な図譜とともに人体構造を記述しベストセラーになり、「切る技術」を「実証に基づく科学」に高めた。

バーゼルスケルトン:現存する最古の骨格標本。ヴェサリウスがバーゼル大学に寄贈した
ヴェサリウスはパドヴァ大学の教授だった。1594年にジェローラモ・ファブリツィオによってパドヴァ大学に世界初の解剖劇場が建てられ、現在も保存されている。その後ヨーロッパ各地に同様の解剖施設がつくられた。

パドヴァ大学、世界初の解剖教室テアトロ・アナトミコ
Morphology ― 人工的な命名
形態学 (Morphology) は morphē(形)+-logia(学) から成り、「形態そのものの理論的研究」を意味する。この語は1796年、詩人であり科学者でもあったドイツのゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe)が命名し、1817年の『Zur Morphologie』で体系化した。近代以降、生物学全般で比較解剖や進化研究と結びついた。
Dissection ― なぜ学問名にならないのか
Dissection はラテン語 dissecare(切り分ける)に由来し、英語では16世紀末に「切り開き」の意味で定着した。しかしこれは終始「手技名」にとどまり、学問全体を指す名称にはなっていない。現在でも「解剖学実習」は anatomy dissection と表現され、dissection=方法、anatomy=知識体系と使い分けられる。
ちなみに、Surgeryにも「logy」がつかない。外科医はかつて理容師が兼務していて、Surgeryも職能として始まったからだろう。こちらはいまでも「手術」という手技(こちらは operation ともいう)、「外科学」という学問の両方の語義で使われている。
AnatomyもSurgeryも「科学」を明示するときは「Anatomical Science(s)」「Surgical Science(s)」という。
解剖学実習の学びにくさ
はじめて解剖実習を学ぶ学生には、どうやって勉強していいかわからないということが少なくないようだ。高校まで教科書と問題集を学ぶことに終始していた学生らにすれば、解剖学を実習という技芸を通じて学ぶのは慣れないにちがいない。Surgery にしろ medicine にしろ、 -logy のつかない学問を学んでいく学生には、最初に越えなければならない障壁ではある。


